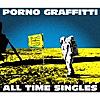2018年8月22日 (水) ~2018年8月26日 (日)、東京都の全労済ホール・スペース・ゼロで演劇プロデュース「クロジ」がお芝居を行っていました。
過去に「クロジ」のお芝居は「パビリオンの星空」を観劇したことがあったのと、好きな役者さんである木村良平さんがパビリオンの星空から3年ぶりに「クロジ」のお芝居に触れることとなったということもあり、「じゃあダメ元で先着チャレンジしてみよっか~」ということでやったらチケットが取れたので友人ともども(友人も木村良平さんのファンです)、前情報が微塵もない状態でいってみました。

ちなみにパビリオンの星空については過去にブログで感想録を書いていますのでよければ。
3年前とかちょっと割と「嘘でしょ…」と真顔になっている今日このごろ。
基本が雑感なので、ポジティブ要素とネガティブ要素が入り混じっていますので注意。
クロジについて
クロジとはそもそもなんぞや?という話ですが、2006年より発足した演劇プロデュース。
主宰は声優の福圓美里さん、女優の松崎亜希子さん。
作品は、華やかな舞台設定で観客の目を楽しませつつも、そこに正直な人間の姿を、時に痛々しく、時に滑稽に描き出す。
発足から数年は、関係性の拗れによる人間心理の生々しさを女性視点で切り取り、特に女性客の共感を集めた。
10周年を過ぎる頃から、クロジのテーマ・メッセージはそのままに、作品をより幅広い世代へ届くエンターティメントとして昇華させることを目指している。
(公式ホームページより)
私の印象は「声優を本職にしている方と舞台を本職にしている方の融合舞台」「小劇団だからこそできる”人の心に突き刺していく”スタイル」の作品が主軸になっているイメージです。
だから、良くも悪くも「うっわ~~~後味わる~~~」ってなったり「ああ……ああ…わかる…わかるからこそ、どちゃくそしんどい…これはメンタルが彫刻刀でガリッガリ削られていく……しんど…ちょっと休もう。寝よう」ってなったりするというか。
「好みが明確に極端に出る」タイプの劇団だと認識しています。
”いと恋めやも”
表題の「いと恋めやも」とは、「本当に恋だろうか、いやそんなことはない」という意味合い。それぞれの意味について。
いと
《副》きわめて。はなはだ。 「それは―(も)たやすいことです」
めやも( 連語 )
〔推量の助動詞「む」の已然形「め」に係助詞「や」、係助詞「も」の付いたもの。「や」は反語、「も」は詠嘆の意を表す〕
推量または意志を反語的に言い表し、それに詠嘆の意が加わったもの。
…だろうか、いや、そんなことはないなあ。
この作品においての「このタイトルを言っている人は誰?」という疑問が生じてきます。それを見終えた上で今一度考えると「ああそうだろうね」っていう納得が生じると言うか。
キャスティング+スタッフ
さっくりとキャスティングを見てみましょう(敬称略)
主演の鴇忠に平野良。
物語に「変化」を与えるヒロイン「つつじ」に白石涼子/ 福圓美里のWキャスト。
一族のちゃらんぽらんな愛に飢えた女・雀に松崎亜希子
一族の長男・蘇芳に沖野晃司。
メガネで偏屈な三男に三原一太、わがままな末娘「撫子」に小日向茜
薄幸の美女・春日香に牧野由依
そして脇に、狩野和馬、杏泉しのぶ、石川ユリコ、中泰雅、中博史。
重要な一族の「お母様」である茜に三石琴乃。
日替わりキャストである臙については沢城千春/平川大輔/江口拓也/阿部敦/島﨑信長/木村良平。
重要部分を担う演出と作は演出に三浦佑介、作に太田守信となっています。
あらすじ
緋桜の屋敷の万年桜
領主は鬼と酌み交わし
笑みを浮かべて内へと招く
いと紅の朱桜
時は大正時代。とある片田舎の丘には立派な洋館がそびえ立っている。そこは華族・緋桜院伯爵家の邸宅である。もちろんその屋敷の意匠もさることながら、なにより人目を引くのが、屋敷の敷地に植えられた、春でもないのに咲き続ける6本の桜の木であった・・・。
所謂さっくりと言ってしまえば「ボーイ・ミーツ・ガール」の鉄板ですよね。
頑なな心を持った当主とはっきりとした田舎娘が結婚し、心を開いていくがその実、人には言えない秘密があって、みたいなかんじです。
基本のベースは狼男や吸血鬼伝説、加えて桜の樹の伝説も添えられていると思います。なんというか「人ではない、けれど妖とも言い切れない、総てにおける中途半端な存在」が自分たちであることへの定義、そのうえで「家」とはなんだ?って話です。
茜(三石琴乃)が桜の精であり、「人と親しくなりたい」が、「人を栄養素として食べてしまう。孤独は辛い。そうだ!子供を作ろう!!夫《人間》は食べてしまうけれど、子供は食べないしね!!」という理論で増やした結果、他の子どもたちが、「愛したい、愛されたい」「でも食欲には逆らえない」という葛藤する物語です。
雑感
セットについて
大正時代の片田舎にある豪邸のリビングがステージになっており、上には万年桜があります。
ステンドグラスには桜の模様が描かれており、螺旋階段のような形で彼らは降りたり登ったり。上手と下手にはそれぞれにソファーが鎮座され、そこも使われていました。両サイドの出っ張りなども使用。セットの移動等はほぼなく、ちょっとした密室劇感もありました。
「王道」か、意外性か
ストーリー部分に関して、私はまったく前知識を入れず、どういう話なのかも分からず、何なら大正時代ということも知らず行ったのですが、開始5分で「ああ、多分これがこうなってこうなんだろうな」という展開が読めてしまいました(笑)
なんというか、いわゆるストーリーとしては王道である「人と人ならざるものの共存」「地位があるものでも苦悩する、身分差」「一歩ずつ始めようとする恋愛」をクロジとして展開したらこうなった、という印象です。
自分の中で「次にお前はこう言う!」とジョセフ・ジョースター*1よろしく予想をたてたものが続いていて、「進研ゼミで習った!」みたいなテンションになってしまったのが事実(笑)
「意外性」はあまりなかったというか、その分「王道」だからこその安心感はありました。
正直クロジという演劇に関して、私が求めていたのは「意外性」「驚き」「ああ~こうくるのか~……!」という人の心を揺さぶるような類のエンターテインメントだったので、今回のこの作品については「こういうこともクロジはできるんだよ」といいたいのかな、と。
前述の「最近のクロジ」についての部分を読む限りだと、そちらにシフトチェンジしていっている傾向にあるのかもしれません。
また、おそらく膨大な量での「カット」があったと思います。
やり取りがまるまるカットされていることも考えられます。
しかしながら、「このセリフの意図、やり取りはどこ?」ってなったり「え?いつの間にそんなことになっていたの?」という疑問が生じてしまったのが惜しい。
三男が「お前のこと家族にしてやんよ~」ののりで試すような言葉を言いつつも《何事もなかった》、蘇芳が香を食さなかったらつつじは知らないままで。
それでああなって「お前家族つったよなぁ!」っていって、逃げ出した彼女に「お前家族っていったじゃん!!帰ってきてよ!!」っていうのは正直私は「えっ……えっ…癇癪起こしまくってるけどお前は何をいってんだ…」と真顔になってしまったわけで。
そのへん、もうワンシーン何か入っていたら、違ったのかもしれないなあとか。俳優さんの三原氏のお芝居が非常によく、何だったら今回のMVPを彼に個人的には出したいぐらい良いな~と思っただけに「?」となったのが惜しい。
後凄い素朴な疑問なのですが、「お前だって豚を食べる、鶏を食べる、牛を食べる、魚を食べる、野菜だって食べる、それとなにが違うんだ?!」って言っていた点についてですが。
彼らはそれを「試した」のかなあとか。愛がわからない三男と撫子はともかくとして、他の「愛を欲している」彼らが、「人と同じ食事をした」という描写はなかったので所謂薄桜鬼的な感覚で「衝動が抗えなかったときは食べる、でも普段は人と同じ」なのか、「毎夜毎夜食べているのか?」ということがわからない。
「人と同じになりたい、けれど人の肉が、血が食したい。耐えても耐えても耐えきれない。欲なのか、それとも”栄養”なのか」という境目について、誰か一言でも言えばキャラクターについて知れるのになあとか。
設定について「ふわっ」としているから、首を傾げてしまうのが残念です。
あと12時になると出てはいけないのは「バレてしまう、食事を食べるから」なのか、はたまた、「欲が増幅されるから」なのか。でもそれならつつじたちが夜を共にした時点で話としておかしくなるわけで……と「???」となってました。
芝居について
皆さん非常に芝居力のある方々で、とてもキャラクターについての解釈が深いな~というのが雑感です。
「お母様」も、演じる人によっては非常に難しいであろう言い回しも、すんなりと言えているのはおそらく三石琴乃さんクラスの演技幅がある人だからだと思います。
牧野由依さんに関しては、私は彼女が「声優・牧野由依」であることを全く知りませんでした。顔と名前が一致していない。
遊佐とツバサ・クロニクルのサクラの人じゃん……と驚いた。あとになって「あー!あの人そうかー!」ってなる。
そういう意味では、今回の芝居のキャストさんたちに関して前知識をまじでほぼゼロ、皆無に等しい状態で見たので「声優さんがどこまでで、どこまでが役者さん」なのかというのが非常に不明瞭でした。だからこそ芝居を掘り下げて見られたのだと思います。
何なら「えっヒロインの子白石涼子ちゃんだったの!?」とも驚いた。全然気づかなかった。
クロジという舞台が、声優/俳優という芝居ジャンルの垣根を超えることで「普段の主軸がどこにいるのか」ということに気付かされる部分もいくつかありました。声の出し方がやっぱり舞台の人と声優さんでは違うのだな、という当たり前のことに気付かされたり。でもその「違うからこその良さ」があるのだろうとも思ったり。
マイクを使わなくともあのステージで響かせることができるというのは素敵なことで、肉声で、こんなにも響くんだな~というところはつい先日、別作品のお芝居での音声トラブルでくぐり抜けた方々のお芝居を見たからこそ、今回も感心したものです。
松崎さんの芝居の通り方が非常によく、どんな芝居においても響く声と、表情をされていたのが良かったです。
だからこそアドリブが内輪ネタ多すぎてもったいないな、とも。
今回のお芝居では、良くも悪くも非常に「内輪」感があり、私には笑いのポイントが分からず、周囲の方々がクスクス笑っている中で「ここで笑う理由はなぜなのだろう?」という現実に引き戻されてしまう点がいくつかありました。
エンターテインメント、「色んな人にみてほしい」という点と、また今回のような「安心して見られる王道ストーリーで新規拡大を狙う」のであれば、もうちょっと入りやすい形で、お芝居としてワンクッション置いてもらえたらな、と。
折角の素敵なお芝居で、その世界に入っている中で「笑わせに来る」を悪いとは言いません。アドリブは全部滅びろ!なんて言うつもりもないし、私はアドリブそのものは大好きです。
ただ、「わからないアドリブをされても、どうしようもない」し、「それがわかるやつだけわかればいい」になってしまうと、ただただ疎外感を感じてしまいます。それってとてもさみしいことで、同じ空間にいるのに部外者みたいで残念なんです。
アドリブに関して(アドリブじゃなく、台本のセリフなのかもしれませんが)、「なんちゃって大正時代」なのか「大正時代」という時代設定をしっかりと基盤におくのか?という疑問がありました。
時代背景、状況を鑑みて「現代語」である「まじかーwww」「それなー!!!」といった言葉/言い回しは、果たしてあの「華族」という設定の上では適していたのかな?とも。キャラクターに適していたか否か、という点で言えば、それこそ長男・蘇芳や酩酊している雀が言うのは納得できたのですが、ほぼ全員が口にしているのを見て「大正時代設定は…?」と寂しくなりました。
そういえは、華族と家族、そして「花」がかけられていたのではないかと今になって気づきました。私たちは華族ですから、なのか、私たちは家族なのですからをかけていたのだとしたら面白い。
後は、あの、多分これは私が「食物」というものに対してそれなりに感情を向けているからなのでしょうが、お芝居の上で、テーブルに足をかけすぎではないかな……?
もちろん彼らが「食人鬼」である以上「食事に対して概念が希薄」「テーブルで食すというよりも今食べたいから食す」のだろう、という部分もあると思うのですが……。
それこそ手すりに足をひっかけるとか、椅子に立つとか、「華族のフリをしているけれど態度が悪い」の描き方は対応できたのではないかな……?なんても思います。
まぁそれは「あえて」やっているのかもしれないな、とは思ったのですが…ちょっともやもやと(笑)
印象に残ったお芝居は三原さん。
とても神経質そうなキャラクターながら、色づけ方が面白かったです。
クロジ『いと恋めやも』
— 三原一太 (@tyapapannga) August 26, 2018
無事終演いたしました!
皆様ほんとにありがとうございます!
終わった瞬間の男性楽屋!
さー!お片付け&打ち上げだー! pic.twitter.com/K8aLyFwZnU
平野良くんのお芝居を見るのはそういえばお久しぶりだな、とふと思いながら見ていました。ハンサム落語のイメージがめちゃくちゃ強いのと、宮下雄也くんのご友人という印象だったんですが、強い言葉が多いキャラクターである鴇忠を演じるのに張るお芝居がとてもよかったように思います。
今回割と前の方で見ていたのですがお芝居の途中で笑いをこらえているシーンがいくつか見えたのは「鴇忠」なのか、それとも「平野くん」なのかがわからない間が見えてしまって、お芝居の世界からひっぱり戻されるという意味でちょっと残念でした(笑)
作品的には「愛されたいと願ってしまった世界が表情を変えた」みたいなアゲハ蝶(ポルノグラフィティ)みを感じるタイプのキャラクターでありながら、それでも突っぱねるという乙女ゲーのセンター感があるお芝居、良かったと思います。つつじとの関係が興味深かった。
日替わりキャストについて
今回の日替わりキャストについて主宰の方々のコメントで「今までクロジで日替わりは無理だと言われていたので試してみたかった」ということでの挑戦だったようです。
総セリフ量と、出演時間で言えばおそらく15分以下だと思います。シーンとしては3~4シーンぐらいでしょうか。
その中でどのように「印象」づけて、どのような解釈をもってどのように挑むのか、が日替わりキャストに求められるお芝居だったのではないでしょうか。
臙は「普通の人」です。人を好きになって、好きになってもらって、この人と一緒にいたい、幸せにしたいと思うのにできなかった。
彼は「好青年」と称されています。まっすぐであると。
で、同時に日替わりキャストに求められるのは臙に対する解釈。
無骨な軍人タイプなのか、柔和がゆえのまっすぐさなのか、これが”初恋”のような初々しさなのか、はたまたこれが”添い遂げたい、最後の恋”と思える運命の恋なのか。
そしてソワレは木村良平くん!
— クロジ (@kuroji_official) August 27, 2018
ゲスト様の役・木野臙は、人食い一族の長女・雀と恋仲になり食べられちゃう役なんですが…
なんか…悪い意味でなく…この人だけ逆に雀が裏切られるんじゃないかと想像させる悪い魅力がありましたね 笑
日替わりゲストのみなさま、本当にありがとうございました! pic.twitter.com/GOkXnLxv6e
私が見たのは木村良平さんのお芝居ですが、彼に関して言えば、一番最後の添い遂げたい、最後の恋”というタイプでしょうか。
好青年だけど、今までの恋を経験したことがあるような雰囲気がありました。なんというか、女性慣れしていらっしゃるというか。彼の中での臙がそういうことを考えて作られていたのかもしれません。優男、というより「色男」ってかんじかな。
とか思ってたら「チャラい」といわれているようでそうかあ…チャラい、に部類するのかあと複雑でした(笑)
チャラいと色男って解釈が違うので、自分の中での解釈が公式では「チャラい」だったのか~~とびっくりしました。
また、プログラムを読んでいて思ったのですが個人的には日替わりキャストは「この人だからやってほしい」というものを踏まえてやってもらいたかった要素があったんですよね。日替わりがゆえに、他者とは違う部分があってもらいたいというか。
この人だから、やってほしい。
自分だからできる、自分だからやる芝居。を、見られたらよいな、と日替わりキャストについてはつくづく思います。
できれば1日の稽古で大丈夫、とかじゃなくて、「この人だからこそできる」ためののお芝居を掘り下げて掘り下げて考えてもらえてたら、良かったのにな~っては思います。
「1日あればできちゃうようなお芝居!」じゃなくて、その少ない時間に魂削って考えて大切に扱ってもらいたいな、と。
まぁもちろんこれはコメント欄でお話されている内容にすぎないので、実際にどうなのかはわからないので、文面そのままを受け取ったに過ぎないのですが(笑)
あと、せっかくなのでイチャイチャしてるとき「いい匂いがする」「たべていい?」ってやり取りの後に「いいですよ」みたいな流れからぐわっと食べられてもよかったというか、どうせなら食べられるところの盛ってる状態から恐怖に歪む、嬌声から叫声に変わるところ、お芝居でみたかったな~~!!!なんても思う。折角のお芝居だからこそ、せっかくの日替わりだからこその「違い」に出会ってみたかったなっていう。
登場人物について
前述したとおり、とても「王道」でした。
お見合いをするに至ったけれど微塵も乗り気じゃないヒロインと、そのヒロインを気に入った母親が「結婚しなさい」という。で、そこから物語が展開していく。
彼らのキャラクター性について考えると、精査されそうだな、ということで。
「カマキリの愛し方」が今回の作品の大きな題としての着想ポイントだったそうです。*2
この点についてちょっと掘り下げて個人的に調べてみたら興味深い記事を見かけました。
「必ず食べてしまうわけではない」ということをこの人は挙げられています。
で、今回のお芝居における部分での「なるほどな」というのは、以下の点。
- カマキリは基本的に眼の前にある動くものに飛びついて食べてしまう習性がある
- メスは交尾のとき、オスのことを「餌ではないもの」と認識できない
(オスは、メスのことをフェロモンで「餌ではない」と識別する) - 悪食であるカマキリは餌が極めて少ない状況では共食いをする
カマキリに関してはファーブル昆虫記でおなじみ。小学校のときに読んだぞ!
彼らの立ち位置でみると、「愛していれば愛しているほど美味しい」というのは、遠野物語にも出てきている話*3がありますね。
愛する人を自分の中に取り込み、「血となり肉となる」からこそ「美味しい」と思うというのはまぁ、そういうたぐいのジャンルならある話で。
そこから「カマキリ」に行き着いているのを見て、だから冒頭茜が威嚇するかのようなシーンではカマキリの窯を構える動作に近い足上げをしたのかなあ、とか。
また、ひとの3大の欲望としては「睡眠欲」「性欲」「食欲」となっているので、そこの「性欲」「食欲」が絡み合っている彼らからすると好きになればなるほど(性欲が増せば増すほど)「おいしそう」「たべたい」になっていくのかなあ。なんて。
食べているとき「餌ではない(=人間だけど自分が食べたくない)もの」という判別ができない、でもフェロモンは放っているから「食べたい(性欲的な意味で)」の絡みつきなのかなあと考察したのですが、そうすると蘇芳の「なぜわかってくれないんだ」は「怒り」からの衝動→食べたいになっているので、ちょっとわからなくなっていく。
後全然関係ないのですが…3男の…体が弱い設定って…どこにあったんですか…!認識できなかったので「えっそうだったの」と最後の挨拶でみて「そーなんだ!」ってなりました。知らなかった。
あと彼らは桜の化身だけど桜そのものでなくても栄養補給できるってことなのかな?
逃げても本体の桜切られたり燃やされたらあかんのでは?とか思ったり。
また、共食いという連鎖でいえば、撫子と長春の関係について「姉弟」「兄妹」「恋人」のふわっとした関係の中で、最後二人になったとき正直私は撫子が長春を食べるのかなって思ってました(笑)
「お腹空いたんだもん」「食べたかったんだもん」「でも長春いないの。どうして?」ってなってそこで愛を知るとかかな……とか。そこまで考えてひどい人間もいたもんだ(笑)って思ったんですが、そこは二人で逃げていましたね。正直「えっ食べないのか」と驚きました。終わってから友達にいったら「人でなし!!(笑)」と言われるという。そりゃそうだ。
なんというか、「因果応報」という部分でいって、最終的に業を背負って焼け死に、燃やされ、桜が散ったのって茜だけで、他の彼らは「各々に任せるわ!」って生きながらえているわけで彼らに対してちょっと俯瞰している「人間側」目線でいうと「あいつら絶対そのまままた喰らうやん……」っていうふうにも思うわけで(笑)
会いたいな~のまま燃え死んだわけでもなく。「やっと会えるね」で死ぬかと思っていた、雀と蘇芳。
でも二人は多分死ななかった(観劇側にゆだねている)。いやあ本当にひどい人間だ(二度目)
桜と”名前”
今回の題材になっている「桜」ですが、桜の木の下には死体が埋まっている、という説があるのは有名ですね。
これは明治時代の小説家・梶井基次郎の短編小説『櫻の樹の下には』の冒頭の文章が元ネタなんですけど。青空文庫にもなっているので、ぜひ読んでもらいたい。
きれいなものには何かある、という部分と儚さとが両立した結果なのですけれども。死体の生き血を吸っているからの「ピンク」なんだ、って説もありますよね。
だからこそ「緋桜院」という名前を付けたのでしょう。緋色の桜。血の桜。皮肉なもんです。そして登場人物の色の名前にもいろいろと考えさせられました。*4
茜=あかね、夕暮れ。やや黒ずんだ赤い色。夕焼けの色。茜空、など。
蘇芳=今昔物語では凝固しかけた血液の表現にも使われている。(近似色に「えんじ色」がある)
鴇忠=おそらくは「朱鷺色」。トキの風切羽の色である。やや紫に近い淡いピンク。黄がちなピンクを想像する人もいる。朱鷺色とも表記する。古名は鴇羽色(ときはいろ)。平安時代には桃花鳥(つき)と呼ばれており、古来日本語の色名には動物からとられたものはほとんどないが、江戸時代から鳶や雀、鶯など身近な鳥の名前が使われるようになり鴇色の表現もその頃だと思われる。
雀色=雀色(すずめいろ)とは、雀の頭のような赤黒い茶色。雀頭色とも。雀が人の住む地域を好む身近な鳥であるためか、植物の名が多い色名のなか、江戸時代に登場したとされる。空が雀色に染まる夕暮れのころを「雀色時」と呼ぶ。
長春=灰色がかった鈍い紅色のことです。長春とは本来は常春の意味。 この色が流行したのは大正時代のことで、落ち着いた色合いから女性たちの人気を集めた。英名では「オールドローズ」とも。
撫子=撫子の花弁のような、柔らかい赤紫色。女の子らしい色。乙女色、とも。
総て赤をベースにした色なんだな、と。桜に近いピンクであり、同時に血を吸う呪われた一族だからこその色。
最後のそれぞれの子供に対しての言葉の投げかけ。「寂しがり屋=人の傍にいる雀」ということなどをいうのかもしれない。そのへん掘り下げてみると見えることが出てきそうですね。
また、鴇とつつじ、雀が「同じ頃に与えられた名前」というのが。
撫子がおとなになれない→撫子=乙女色=女の子であることへの固執 かな、とか。
ちなみにヒロインのツツジですけれども。
赤のツツジの花言葉は「恋の喜び」。 白のツツジの花言葉は「初恋」。なんですよね。
これは「本当に恋だろうか、いやそんなことはない」という横で「恋をした、愛を覚えた」という女の子の対比かなとか。
そんなことを思いながら、東雲は朝焼けな色だからあの場所に入れたのかとか。
部外者と呼ばれた女性二人は色の部類としてそこに入れなかったから、なのかな、とか。いろんなことを考えていたりします。
あとあの長春友達に噛み付いたっていうけどワインレッドの服で震えてたから全く血で染まってるのが分からなくて「?」てなったので白いシャツで赤く染まってたら分かったのになあと。あとで言われてそうなの?ってなったのは惜しかった。
血で震えたのに、怪我して動かないかと思ってたのにつつじに矛先すぐ向けてるのに体力あるやん!とちょっと思ったり(笑)
そういえば少し展開で不思議だった点で、旦那は食えるけど子供は食べない、というのは何故だろうと。
だって愛してるのは明確で、好きなわけで。多分愛を、性欲とか親子ではない愛情として食べる、なのだろうけど、でも半分人間なら、甘噛みくらいは…するのでは…?とか思ってました笑 そうすると話おかしくなるんだけど!ちょっと設定としてここどうなのか知りたいなあってなったので。
また、作中に出てくる人々のモデルは多分この人かな、というのがそれぞれにいて、蘇芳と鴇忠は坂本龍馬⇔土方歳三かな、と思うし(服装や行動の類似)、茜に関してはイメージの中にエリザベート・バートリがいそうだなあとか思うし。
エリザベート・バートリ調べると圧倒的に今FGOばっかり出るのがあれなんですけど!(笑)
まぁ私もベルばらからしった類の人間なのですが(外伝に出てくる)、美容に固執してるけど結構類似はあるだろうな~ても思う。
だから掘り下げていけば他のメンバーもそれぞれ見えるものがありそう。
友人の見解
最後のシーンについて、友人が「印象的だったのは最後の車椅子のシーンで家族みんなテーブルについてた。上手に鴇忠とつつじがいるんだけど、他の家族は正面を向いていて、茜だけが2人を優しい顔で見ていた。あれはお母さんだけは2人が見えてるのかなって。母にとっては大事な子なんだなって思えた」と言っていたのが印象に残りました。
私は家族が一つ終わり、また一つ新しい家族ができ、その差異であるかなと思っていたのと、母親が送った≪呪い≫が形を変えたものが、奇跡という形での呼び起こしなのかと思ってました。
人によって見解違うの面白いですね。
これからのクロジについて
今回のクロジは「今年一年はやらない予定だったけどいろんなことが重なって実現できた」というお話だったので、イレギュラーのイレギュラーな結果のお話、展開、ステージであったと思います。
従来の形の「うっわ~~~心削ってくるねえ~~~」ってなるのか、それとも大衆向けに新たに築いていくのか。どんな風に変わっていくのか、それとも今まで作ってきたものを基盤にしつつも積み重ねるのか。
どんな風に作っていくのか、興味深く見守りたいと思います。